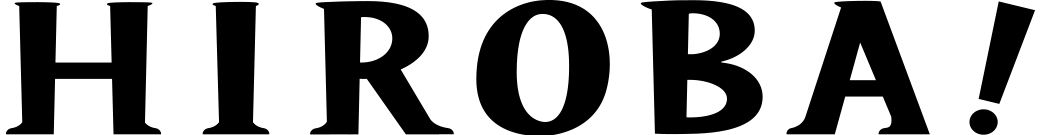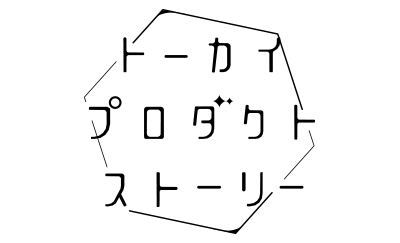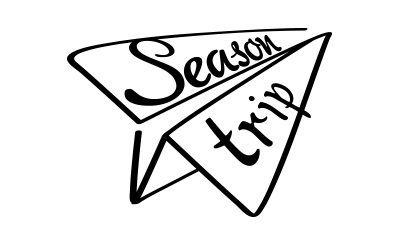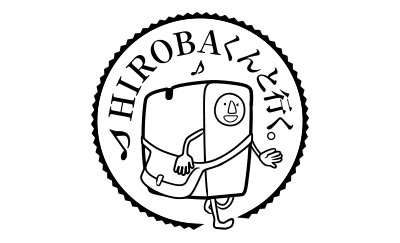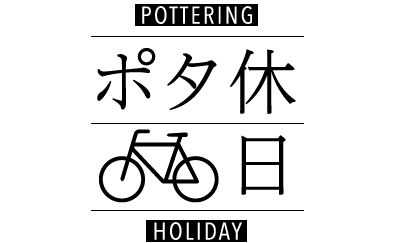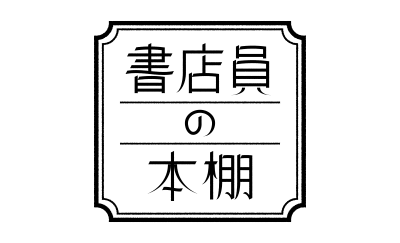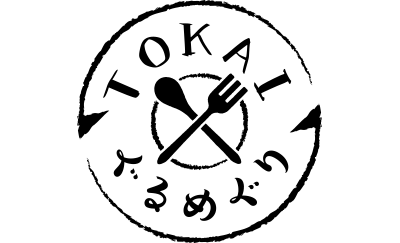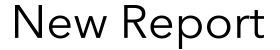飛騨高山の工房「真工藝」で生まれた、素朴で愛らしい木版手染ぬいぐるみ。十二支の動物や自然のものをモチーフに、木版を用いて生木綿を染めつけするという独自の手法で作られています。前編では、開発までの経緯やデザイン秘話を紹介しました。後編となる今回は、ひとつのぬいぐるみができるまでの実際の制作過程を覗きます。

↑集めて並べてもかわいい、十二支のぬいぐるみシリーズ。
一度に全色を刷る、紙版画とは違った着色方法
真工藝の木版手染ぬいぐるみは、いわゆる「作家もの」ではなく50人ほどの職人たちによる「民芸品」。版を刷る・縫い合わせる・詰めるといった工程ごとに職人さんがいます。

↑ご主人とともに木版手染ぬいぐるみを手掛ける「真工藝」の田中博子さん。

↑複数の色が混ざらないように深く版を彫るため、厚い版木を使います。
一般的に紙に刷る版画は、使う色別にいくつも版を重ねて1つの版画を完成させていくもの。ぬいぐるみの場合は布に刷ることになりますが、布は伸縮性があり、紙のようにはいきません。そこで、一度に全色を刷るという手法をとることに。
「1つの版に複数の色をのせるのは、難しい作業。先にのせた色が乾く前に全ての色をのせる必要があるため、スピード感が重要になってきます」。

↑染料は水に溶かして使うため日持ちせず、こまめに色を作り直す必要があります。
染料はそのままの色で使うこともありますが、混ぜ合わせて微妙な色を調整することも。この染料の色をつくる作業が、制作の過程で手間がかかるところ。染料は状態によって色が少し変わることもあり、同じ分量で同じ染料を混ぜても全く同じ色にはならないのです。
また、木版の状態によっても水分の吸い込み具合が変わります。染料の具合を見ながら色を濃くしたり、木版の具合を見ながら染料を塗る量を多めにしたりと調整するそう。

↑ぬいぐるみの生地には、織りあげたまま漂白していない生木綿を使用。
布の状態も、同じ規格であっても油分が多い・少ないなど多少違うもの。自然から生まれた素材を使っているからこそ、毎回同じようにはいきません。
もみ殻を詰め、蒸して色を定着
木版で染めた布を縫い合わせたら、次は中にもみ殻を詰める作業。開発当初は、そば殻を入れてみたり綿を入れてみたりと、中に詰める素材も色々と試したそう。「軽すぎず重すぎず、手に持ったときに程良い重みで安定感のあるもみ殻に落ち着きました」。

↑ひとつひとつ丁寧にもみ殻を詰めていきます。

↑専用の大きい蒸し器で、長時間熱します。
色を定着させるため、最後はぬいぐるみを蒸していきます。すると、染料が熱に反応して発色。赤色が明るくなったり茶色が濃くなったり、色によって発色の仕方が変わります。染料を調整して色を作るときにも、蒸した後のことを見込んで色を調整しているそう。蒸し上がりを見て、もし想定していた色と違った場合は染料を作り直します。
飛騨高山の工房から世界まで広がるぬいぐるみ

↑大・小と並んだ真鴨と子鴨のぬいぐるみの親子。
こうした手間暇をかけて完成する「木版手染ぬいぐるみ」。今では全国各地、さらには海外にまで販売を拡大しています。アメリカやヨーロッパ、アジア圏でも取り扱いが増えているのだとか。最近はものづくりに興味を持つ若い人も増え、わざわざ遠方から高山まで訪れる人もいるそうです。

↑思わず自分用にも買い物。オリジナルの紙袋も味があります。
一貫して手づくりにこだわり、温かみが感じられるかわいいぬいぐるみ。布に版画を刷り、縫い合わせ、蒸して仕上げる…真工藝独自の手法があるからこそ、この温かい風合いが生まれるのです。
(写真:西澤智子 文:齊藤美幸)
前編はこちら