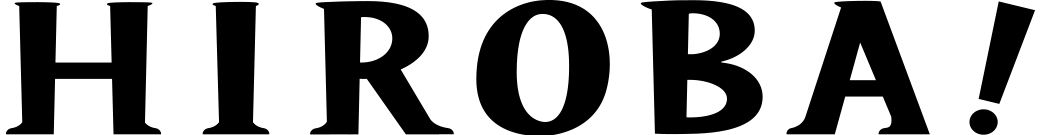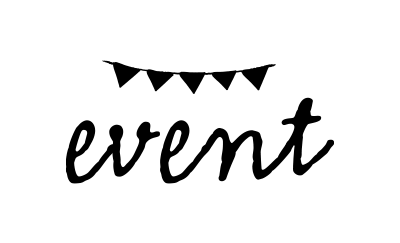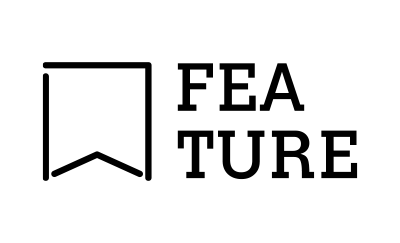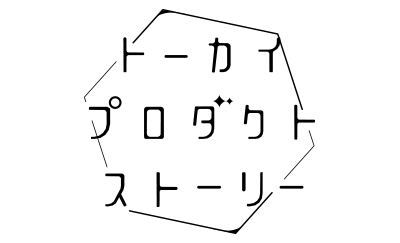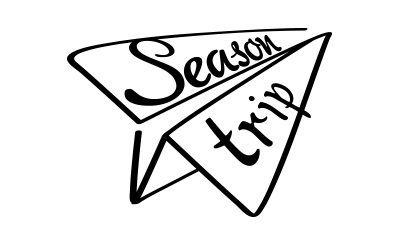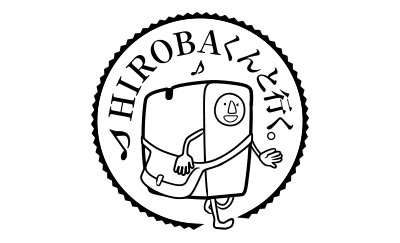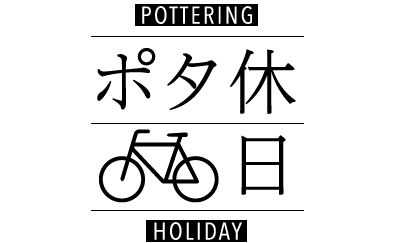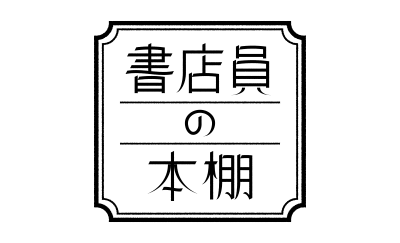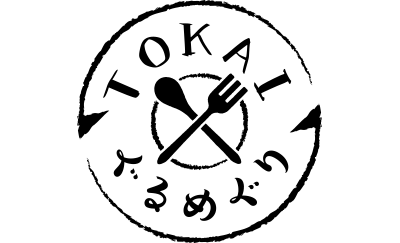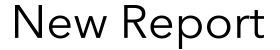岐阜県を流れる清流・長良川。夏季は鵜飼の見物でにぎわいますが、2006年からある取り組みが始まり、冬の風物詩となっていることをご存知でしょうか。こよみのよぶね―― 毎年冬至の日になると、鵜飼観覧船乗り場から長良川近くのプロムナード一帯で、色とりどりの和紙で彩られた行燈をのせた屋形船が、静かに川を流れていきます。12種類ある行燈はそれぞれ、1月から12月を表現し、数字のかたちに。観客たちはこの愛らしい「こよみのよぶね」を眺めながら、ゆく年の1年を振り返り、また、くる年の1年に思いを馳せるのです。仕掛人は、80年代からさまざまなアートプロジェクトを手掛けてきたアーティスト・日比野克彦さん。出身地である岐阜県でどんなアートシーンを打ち出していきたいのか。その想いに迫りました。
― 日比野さんと言えば、80年代に段ボールアートで一世を風靡した、というイメージを持っている方が多いと思います。日比野さんにとって、アートとは?
日比野:今までいろんな人と関わりながら社会の中で作品を発表してきました。そういうのを、アートプロジェクトっていうんだけど、僕は元々、大学でデザインを専攻していたことがきっかけになっています。ものはすべて機能を持っている。例えばポスターなら告知をするという機能、プロダクトなら生活便利機能。そして、世の中でいろいろな使われ方をするという機能を想定してつくられるのがデザイン。だから、僕のアートプロジェクトも、ひとりでつくって終わりではなく、社会の中で誰かと一緒にそのデザインを使って交流することを目的としてきました。

― 日比野さんは東京拠点で活動されながらも、89年には岐阜新聞の110周年記念特集号を手掛けるなど、出身地・岐阜の人たちとの関わりもずっと大事にされてきましたよね?
日比野:岐阜は地元だからもちろん愛着があったけど、それだけじゃなくて、当時から名古屋でも福岡でも、いいプロデューサーに出会うことで、いろいろな作品を発表することができました。商業施設の中にオブジェをつくったり、壁画を描いたりして。でも、地方でやるからといって、「地方色」を意識することは、実はあまりなかったんです。僕が当時つくったオブジェを東京に置いたって、福岡に置いたって、観る人はきっと「東京らしさ」「福岡らしさ」を感じなかったはず。つまりそれは「その土地ならでは」を意識したことにはならない。
― ここじゃなきゃ、この作品はだめ!という意識はなかったと。
日比野:そうですね。土地が持っている長年の歴史というか、「場のチカラ」を利用し始めたのは21世紀になってからです。それまでは、地域も早く都会のようになりたいというような、一極集中の考え方で都市政策が進められていました。でも、だんだん環境問題や人口問題が出てきて、「みんなが東京に向かってどうするんだ。それじゃあ地球がもたないよ」って、人々の意識が変化してきた。地域らしさを魅力にしていかないと、地球がおかしくなる。それで、地域の価値を見直していこうという時代の流れの中で、僕のアートプロジェクトも変化してきたんだと思います。

― 長良川で始めた「こよみのよぶね」も、地域の価値を活用したアートプロジェクトのひとつですね。今年で11回目を迎えるわけですが、どんな場面が心に残っていますか?
日比野:最初は本当に人集めが大変で(笑)。岐阜公園で作業を始めたんだけど、告知した新聞記事を読んできたという女性が、お餅を差し入れてくれました。嬉しかったなぁ。結局初回のプロジェクトメンバーは5人くらい。それでもなんとか8月からつくり始めて、冬至の日には12か月分のこよみのよぶねを長良川に浮かべることができました。
― 最初は失敗談も?
日比野:8月に作業を始めたから、数字の「8」の行燈からつくったんだけど、最初はまだ水かさの計算ができてなくて(笑)。試しに流してみたら「8」の上の方が橋にぶつかって折れてしまった。あと、その時の干支が戌年だったから、紙で犬型の船をつくったんだけど、それも水を含んで浮かばなくなっちゃったね。ちなみに、舟をこぐのは鵜舟の船頭さんにお願いしているんだけど、最初は舟の重心が上にいっちゃったりとか、鵜飼をやる時と全く勝手が違って、苦労したって話も聞いてる。
― 失敗を乗り越えて、今はどのように作業をされているんですか?
日比野:今では参加者も増え、12か月分を12のチームに割り振って作業するようになりました。全体を統括するリーダー(※)がいて、地域の集会所や学校などに集まってチームごとに和紙を切ったり貼ったりしながら、舟にのせる「数字行燈」づくりを進めてもらっています。初回は僕がスケッチを描いていましたが、今では12の参加チームが描いたスケッチを見て、多少アドバイスをするぐらいです。みなさん、岐阜が好きで意欲的に取り組んでいますよ。
(※2016年~2017年のリーダーは住 公輔さんと吉川 章さん。こよみのよぶねがスタートして10年目を迎え、また、2017年には岐阜に織田信長公が入場して450年を迎えるなど、節目の年であることから、人と街がつながる未来をイメージし、1年目から12年目までの干支のかたちの制作も検討しているという。)

― 年々、コミュニティが広がっているんですね! 数字行燈は1月に長良天神まで運ばれ、竹も和紙もすべて燃やされるんですね。
日比野:全部バラバラにして燃やすっていうのは、最初から決めていました。参加者の方からは「燃やすなんてもったいない」と言われることもありますが、もし来年までとっておけば「つくらなくていい」という状態になり、地域のみんなが集まる機会がなくなってしまう。初回につくった数字行燈をずっと使いまわしていたら、コミュニティはこんなに拡大していなかったと思います。
― この一連のアートプロジェクトは、古くから地域に根付くお祭りを思い起こさせますね。
日比野:そうですよね。毎年必ず冬至の日にやっているのも、人間の都合ではなく、自然のリズムに人間が合わせるためなんです。自然のリズムを優先するから「俺都合悪いから、ちょっと開催日ずらしていい?」っていうのは、できない。過去、冬至が金曜日だった年に、土曜日の方が観客が集まるから、1日ずらさないかという意見も出ましたが、それはやめましょうと言いました。夜が最も長い冬至の日にやることが大事。だから、人間の都合でずらさない。その感覚は、これからもブレることはありません。
― 地域らしさに、歴史や自然のチカラを融合させたアートプロジェクト。取材の最初にあった“場のチカラ”のお話につながりますね。
日比野:ええ。「この場所で、この瞬間でなければできないもの」を手掛けていきたいと思っています。僕の作品には舟や川のモチーフが多いのですが、それは僕が岐阜市に生まれ、幼い頃から長良川で泳いで育ったから。高山市に生まれていたら、また違っていたと思います。


― 最後の質問ですが、日比野さんは2015年から岐阜県美術館の館長に就任されていますが、一人の岐阜県出身者として、そして、アーティストとして、この街とどんなふうに関わっていきたいと考えていますか?
日比野:プロジェクトや作品をつくって終わりではなく、つくったものを見てもらって、つくり手と見る側とで気持ちが交換できたときに、初めてそれは作品と言えると思っています。「こよみのよぶね」のように。まずそのきっかけとして、特別な美術愛好家だけでなく、さまざまな人たちが、さまざまな視点でアートに触れることができる空間を打ち出していきたいですね。そして、岐阜ならではの地域性が世界から注目されるように、常に岐阜から世界を見つめ、発信する意識を持ち続けていきたいと思います。