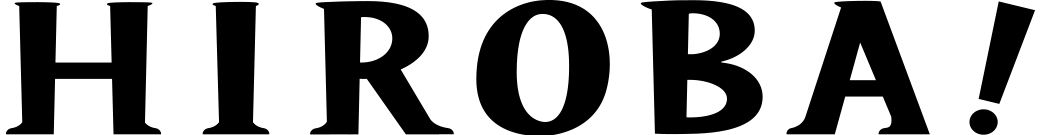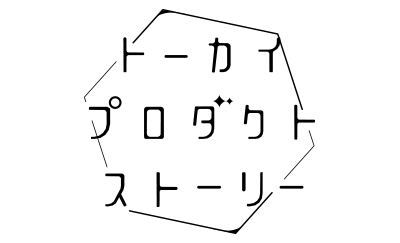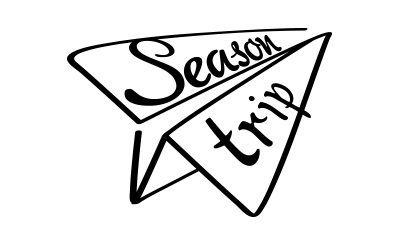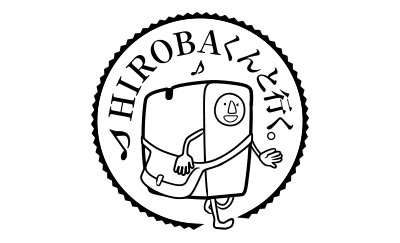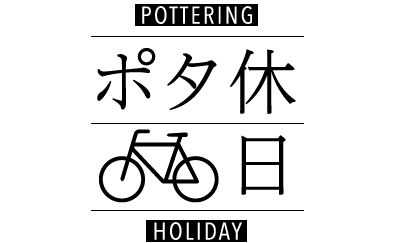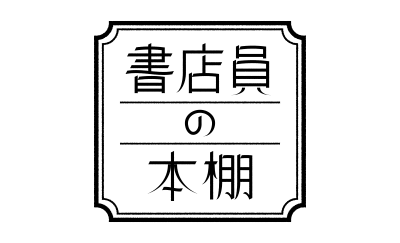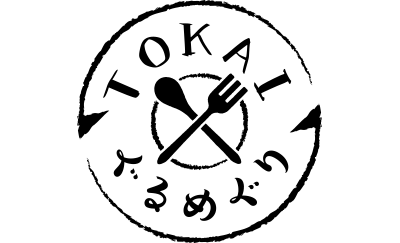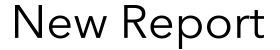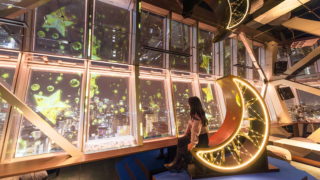↑真工藝で作られる、木版手染ぬいぐるみ。野鳥シリーズはさまざまな種類が展開されています。
お土産屋の設計から始まり、商品開発へ

↑築200年ほどと思わしき歴史ある建物を改装した、真工藝の店舗兼工房。

↑店内にはぬいぐるみをはじめ、木版画のデザインを基調としたポストカードや手ぬぐいなどオリジナルの品が並びます。
「木版手染ぬいぐるみを作りはじめたのは、父と母。元々、インテリアデザインなどを手掛ける会社を経営していたのですが、土産店の設計を頼まれた際に何か商品も作ってほしいと頼まれて…」と話す田中さん。父は油絵をたしなみ、市の展覧会委員を。母は京都の家元で「絵更紗」という染色の修行を積んだ染色家でもあったといいます。

↑先代から真工藝を引き継ぐ田中さん。ご主人とともに新しい商品も生み出しています。
「版画を使って何かやってみようと、まず作ったのは高山の風景を手刷りしたお皿。そのうちに、布に刷って小物入れを作るようになりました。動物や魚が好きだった父。自然のものをモチーフとして、布製のぬいぐるみを作ってみることに。最初にできたのがキジと馬です」。これが木版手染ぬいぐるみの始まりでした。
すべてのぬいぐるみが物語のあるデザインに

↑記念すべき最初の木版手染ぬいぐるみ、キジと馬。もちろん現在も店頭に並んでいます。
真工藝の木版手染ぬいぐるみには、どのモチーフにも物語が込められています。この馬は、飛騨一之宮の田畑を夜な夜な食い荒らすため、眼球を抜き取られてしまったという逸話のある“稲喰馬”。雨乞いにご利益があるとも伝えられているそう。デザインに稲が組み込まれていたりと、物語を知ってからぬいぐるみを見るとますます芸の細かさに気付きます。

↑“陣屋福猫”の物語が生まれた「高山陣屋」がある場所は、真工藝のすぐ近く。
こちらのかわいい猫は、江戸時代の役所である「高山陣屋」にゆかりがあるもの。
庭の松の木の下で、鯉を見ていたという姫。突然、猫が狂気のように姫の着物の裾を引っ張ったため、陣屋の郡代が猫の首を打ち落としました。すると、飛んだ首は松の木の上にいた大蛇に噛みつき、大蛇は死に果てたといいます。猫は大蛇から姫を守ろうとしていたのです。この物語から“陣屋福猫”は、災いから守り福を招く御守と信じられているのだとか。

↑すべて手刷りするため、全く同じ仕上がりのぬいぐるみはひとつとしてないのも魅力。自分好みのぬいぐるみを見つけてみては。
現在は、ご主人が中心となって家族の意見を取り入れながらデザインを練っています。デザインが決まるまでが、開発で1番の苦労。「どんなイメージで作るか決まった後、平面に刷ったものを立体に仕上がるように形を作る必要があります。試作を何度も作り、試行錯誤を繰り返しました」。
毎年集めたくなる十二支のぬいぐるみ

↑ころんとした形と表情がかわいい、“ごめんね犬”。
十二支のぬいぐるみは、1年にひとつずつ制作して12年がかりですべての干支を作り上げました。今では、干支を3周以上まわるくらい続いている人気のシリーズ。同じ干支でも、その年ごとにデザインを見直しています。
「例えば戌年に最初に作った犬は、かつて飼っていた猟犬に似せ、少しすねたような顔をしていたので“すね犬”なんて呼んでいました」。偶然にも、父も祖母も姉も妹も戌年生まれで、犬が大好きな一家なのだそう。
その後、犬のデザインを和風に変更。すね犬は作らなくなっていましたが、2011年にデザインをアレンジして復刻しました。「今度は、謝っているように見える“ごめんね犬”。こちらもお気に入りです」と微笑む田中さん。

↑2019年の干支、猪のぬいぐるみ。大きい猪と小さい猪で模様を変えているので、両方並べて置くのもかわいいですね。
2019年の干支は「亥(い)」。猪は、笹原を走り、猪突猛進しているところをイメージしたデザインです。よく見ると笹が描かれています。毎年、その年の干支を買って十二支を集めるのを楽しみにしている方も多いそう。12年かけて干支を全て集めるなんて、粋な趣味ができそうです。
後編では、独自に研究したという実際の制作過程を紹介。ひとつのぬいぐるみができるまでに秘められた、数々の工夫を覗きます。
(写真:西澤智子 文:齊藤美幸)
後編はこちら